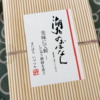奥琵琶湖、陸の孤島 – 菅浦
南北に長い琵琶湖の最北端、岸から細長く突き出した岬の先端部に菅浦の集落はある。眼前の湖と背後の険しい山々に囲まれたわずかな土地に民家が密集している。

湖に近い家屋は前面が石垣で守られ、入江には大型の防波堤が築かれている。湖に津波なんてあるのだろうかと思ったが、強風の日には高波が来ることもあるそうだ。

昭和41年に湖岸道路が開通するまでは舟が唯一の交通手段であり、あとは険しい裏山を徒歩で越えていくしか外部と交流する手段がなかった。
隔絶された環境なので集落の結束は固く、中世には惣村を形成して自治を行った。現在は集落の東西にだけ残る四足門もかつては東西南北にあり、集落に入る者を厳しく監視したという。

須賀神社に秘蔵されていた膨大な文書には、村の掟や住民の活動、近隣の大浦荘との争いや戦国大名浅井氏の支配など、中世から近世にかけての生活と歴史が克明に記録されていた。中世村落の暮らしを窺い知ることができる一級資料だ。菅浦文書と呼ばれるこの記録集は国宝にも指定されている。村の記録が国の宝になったのだ。
菅浦文書が発見された須賀神社は集落の西の外れにある。長い参道を登っていくと、石段の手前で靴を脱ぎ、用意された上履きに履き替えるよう指示書きがあった。インドなどの寺院では土足厳禁が当たり前だが、国内では初めて遭遇した。いまなお古いしきたりが生きているのだろう。

私自身は町育ちであり、こういった田舎の小村で生まれ育つというのがどういうことなのか、想像はできても実感はない。こんな場所で子供時代を過ごしてみたかったなという憧れもあるが、成長して集落を出ていく気持ちもよくわかる。
中世より昭和まで戸数にも人口にも大きな変化はなかったものの、平成以降は徐々に減り始め、近年には戸数は半減し人口は4分の1以下になってしまった。集落内で出会うのは高齢者ばかりで、しかもその数は多くはない。中世より続く集落も、そう遠くはない未来に終わりを迎えてしまうのだろうか。
2025年2月